こんにちは。ともぴぃです。
雨があがったものの昨日は強風。
これをもろに受けたジャーマンカモミールさんたちがのきなみ倒れかけ…( ̄▽ ̄)。こぼれ種で勝手に育ったモノなので点在してるんですよね〜この子たち。

ジャーマンカモミールは冬の間は背丈も低くどしっとした感じなんですが、温かくなって一気に伸びると倒れやすくなります。花を摘んでいくことで脇芽のようなものがでてもう少しはマシになるとは思うんですけどね。
この秋はもっとジャーマンカモミールを種からたくさん育てて密集して植えておきたいなぁと思ってます。そうすると育ったときお互いに支え合えるだろうし。
でもやっぱり思うのは…
こぼれ種で育ったものは最強。
文句なしで強いっ!!
そもそも種って水、光、気温の条件が揃わないと発芽しないんですよね。
寒い時期に部屋で発芽させたものなどはある程度条件を作り出して育ってるものなので、外に出すタイミングでダメになったりすることもあります。が、自らその条件に適応して芽をだして育ってるこぼれ種組はそれを乗り越える力があるように感じます。
それを私が個人的に顕著に感じているのがマリーゴールド。
ここ数年毎年種から育てていますが、3月や4月に種おろしすると朝晩がまだ寒いので部屋にいれてあげています。それでもちょっとしたことで葉の色がすぐ紫になってたりするんですよね〜。
でも最初っからこぼれ種で芽を出した子はずーっと外にいるのに緑のままでイキイキしてる。この差はきっと適応力なんでしょうね。強いわ!!
あ、そうそう。
ちょっと余談ですが…
以前、ひとつの植物から採れる種は同じ条件下で100%の発芽率にならないようになってるということを聞いたことがあるんです。平たく言えばイレギュラーの状況下での発芽条件を持ってる子が少しいるってことなんですが、それはその植物がいつもと違う条件下になっても発芽できる子がいることで、どんなときでも種を繋いでいける可能性が高くなるからなんだとか。すごくないですか?
恐るべし自然のリスクマネジメント!
次の世代へ命をつなぐためのすばらしいメカニズムだなぁと感心しました。もしかしたら、発芽率が悪い植物は繊細なだけじゃなくて、それだけ条件が厳しくて色んな条件を持ってる子がいるってことなのかもしれないですね。
…というわけで!
話は戻りますが、こぼれ種。
自らタイミングを選んで芽を出してきた子たちを今日は紹介してみようかなと思います。
こぼれ種の芽吹き2025年5月
マリーゴールド
マリーゴールドはオレンジも黄色も、2022年に育ててから毎年必ずどこかで芽を見つけてます。こぼれ種の子はしっかり根付くのか大株になる傾向があるように感じます。

青じそ・裏べに紫蘇
青じそはこぼれ種発芽を狙って
意図的に枯れてもずーっと畝に残してたのでうれしいです!
紫蘇、大好きなのであちこちに育ってほしいなー。


裏べに紫蘇、今年もいたっ!
特徴的な葉なので見つけやすいです。実はここだけの話し、我が家では使い勝手は青じそのほうがいいという結論になり種取りもしてないんですが^^;;、律儀に毎年顔を出してくれてます。
ジャーマンカモミール
あちこちでかなりたくさん芽をだしてくれました。
数は圧倒的にナンバーワン!!そろそろ収穫も始めますよ〜。


フォホーノビーツ
なななんとっ!
去年種取りしたビーツ、なんとこぼれ種もあったようです!!
これはびっくりだわ〜!!

すくすく育ってほしい(収穫したい)。
4月下旬に種おろししたビーツはまだまだ小さいのでこの大きさになるまでは時間がかかりそうです。
こぼれ種はワクワクの宝庫!
もうね、見つけたらめちゃくちゃ嬉しいです!
お宝発見って感じで。
あっ!こんなところにっ!!
ってテンションがあがるーっ
今後期待したいのは、
ハーブではバジル系、野菜ではリーフレタス。
どちらも種が落ちてくれないかなーと残してたんですが…出てくるものはあるでしょうか?草がいっぱいだからレタスは特に氣付きにくいかもしれませんが…www。
チャービルも出てきたらうれしいけど彼らのいた場所は畝を作り直したので厳しいかな。
今後も種取りをしながら、こうしたこぼれ種の発見も楽しめたらいいなーと思ってます。これも種取りをするところまで残す醍醐味のひとつ。植物の一生を見守る感じが楽しいですよね。そしてこぼれ種組の凜とした雰囲気にパワーを貰ってます。
みんながんばって育ってねー!!
では、ウキウキでいきましょう。
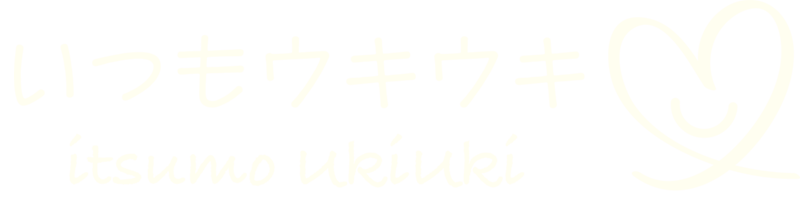
 loading="eager" fetchpriority="high" decoding="async"
loading="eager" fetchpriority="high" decoding="async"
コメント
コメント一覧 (2件)
ほんと、種まきしたのは発芽不良なのに
野良は強いよねぇ~
でも、間引き頑張らないと、やたら密植するでしょう~
わが家では、リーフレタスとオカノリが野生化してる~
(^^)
このはさーん、こんばんは。
ほんとに!!!!野生は強いなぁってつくづく感心しちゃいます。
まだウチでは密植するほど生えてきたことがないのですが、そうなったら間引きしまくって食べちゃいたい(笑)。
わー、リーフレタス、我が家はまだ今回は野良ちゃんが出てきてないようですが、このはさんみたいに野良レタスを楽しめるようになるのが目標ですっ!!